青い眼が欲しい(トニ・モリスン:ハヤカワepi文庫)
読み終わった後の、ぐ、と気分が沈むような感じがどうにも。
著者のトニ・モリスンは1993年にノーベル賞を受賞。この「青い眼がほしい」は1970年に書かれたデビュー作になる。
もの凄く大ざっぱに言うと、アメリカにおける黒人社会に蔓延する貧困や差別の問題を描き出しているのだろうけど、じゃあ差別に抵抗して勇気を持って立ち上がるだとか、人種の壁を越えた融和だとか、解放のための戦いとかそういう話では全くなくて、もうただひたすら、アメリカで黒人として生きるという日々の現実だけがある。
厳然としていまここに差別はあるし、生活はやはり貧しいし、けれどそれを打倒しようなどと登場人物が思っているわけでもなく、ただそういう現実の中で生きている。語り手の少女も黒人で、けっして満足のいく暮らしをしているわけではないけれど、そんな「少女」から見ても更に悲惨な黒人一家の崩壊の様子が描かれているわけで。
もう絶対、読後感なんていいわけない。
可哀想とか悲しいというより、もうなんかツライ。ピコーラ(本作の実質的な主人公とも言うべき、特別悲惨な生活を送っている黒人少女)の、叶うはずもない馬鹿げた「お願い」が、けれど「彼女が幸せになるための方法」としては確かに正しいと認識した途端、何ともいえない脱力感がある。同時に、その辛さに奇妙に納得してしまうところが、この本の面白さ(と表現するのも躊躇われるが)だと思います。
以下、ネタバレ含むので未読の方は注意。
主な登場人物
・クローディア:本作の主な語り手。黒人の少女
・フリーダ:クローディアの姉
・ピコーラ:本作の実質的な主人公。平均的な黒人家庭よりなお貧しい家に生まれた
・チョリー:ピコーラの父。生まれてすぐ母親に捨てられている
・ポーリーン:ピコーラの母。白人の家に家政婦として雇われ、信用されている。
・ソープヘッド:インチキ霊媒師。ピコーラから相談を受ける
丁寧に崩壊していく人たちの物語
物語の語り手である「私」ことクローディアは、オハイオ州に暮らすごくありきたりな黒人の少女として暮らしている。家はけっして裕福ではないが、暮らしていけないほど貧しくもない。歳の近い姉がいて、言い争ったりしながらもそれなりに仲良く過ごしている。そういうクローディアの家に、ピコーラという黒人の少女が預けられてきた。
クローディアの家も「どうにか暮らしていける」だけでその生活は不安定であり、姉妹ともに恵まれているわけではないのだけれど、そのクローディアと姉のフリーダの元にやってきたピコーラという少女は更に悲惨な境遇に置かれている。父親と母親は一般的な黒人より更に貧しく、それに醜い。その二人から生まれたピコーラも醜い(少なくとも、周囲からはそう判断されている)。
ピコーラの父親のチョリーは生まれてすぐ母親に捨てられた男で、育ての親であった伯母を失った後には最低限の生活しかできていない。母親のポーリーンは家事の腕前でもって白人の家に家政婦として雇われ信用されているが、自分の家族に対しては冷淡で娘にも厳しくあたる。そういう両親のもとでピコーラは萎縮しながら日々を送り、学校では同じ黒人の男の子たちからその容姿が原因で苛められていた。そうした日々の中で、いつしかピコーラはたった一つの願いが叶うことをひたすらに夢見るようになっていた。自分が不幸なのは、この醜い容姿のせい。私が青い眼をしていたら、きっと幸せになれたはず。だから青い眼が欲しい——
もうこの時点でわりと悲惨な話なんですけど、話が進むにつれてピコーラの人生はますます勢いよく、ますます悲惨になっていくわけです。最初から不幸だったピコーラの一家はますます不幸になって更に家族としての最低限の形すら失って崩壊していく。
ピコーラの父親のチョリーは生まれすぐに母親に捨てられ伯母に育てられているのですが、伯母の死後に実父(と思われる男)を見つけてもそれで何か好転するわけでもなく、人々に蔑まれながらどうにか生きてきた。それでもポーリーン(ピコーラの母)と出会って愛し合って結婚するわけですが、両親からまともな愛情を得たことがなくその場しのぎの生き方をしてきた男が、結婚したからといって急にまともになれるわけでもない。初めて得てしまった家族という重圧に負けてフラフラになり、そんな夫に妻は苛立つ。そんな二人でも子供の誕生を切っ掛けに夫婦仲を取り戻しかけるものの、やはり良い時期は長く続かず、だらしない夫と勤勉だが狷介な妻に戻って行く。
こうした二人の元に生まれたピコーラは内面的には素直で優しい少女に育つけれど、貧しさと醜さはどこまでも彼女の枷になる。ピコーラは自分の不幸の源は自分が醜いこと、そして黒人であることだと考えていて、「(白人の女の子のような)青い眼がほしい」と願いながら生きていく。そしてある日、ついに彼女に決定的な不幸が襲いかかってきた。酔って家に戻った父のチョリーが、台所仕事をしていたピコーラを暴行し、ピコーラは父親の子を身ごもってしまう。
この本を読み始めるとまず最初に「家があります。緑と白の家です」という文章があるんですね。いわゆる「白い家に小さな庭、暖炉があって犬がいて……」的な、幸せな家庭の理想像みたいなヤツです。そのあまり長くない文章が、最初は普通に、次に句読点がなくなり、最後には全文ひらがなで書かれるようになって、最初に読んだ時は「なんだこれ?」と首を捻るんですが、本分を読み進めていくと「あ、これはピコーラが壊れていくところなんだ」と分かるわけです。あの部分、英語ではどうなっているのか知りませんが、この小説の全体の構造、「一つ一つ積み重ねて一つの家、一人の少女が崩壊していく様子」という「仕組み」を象徴しているなと思いました。
暴行を受けてちょっとおかしくなりつつあるピコーラは、ソープヘッドというインチキ霊媒を訪ねます。そしてかねてからの「夢」を打ち明ける。「青い眼が欲しい」というあの夢です。
そんな「夢」を叶えてくれるようにと頼まれたソープヘッドは、もちろんギョッとします。できるわけない。ソープヘッドはもちろん、ピコーラのその夢が滅茶苦茶な願望であることは分かっているのですが、同時に完全に正しい望みであることも理解する。実際、ピコーラがなぜ不幸なのかというと、彼女が醜いからなのです。もっと言ってしまえば、彼女の目が青くないから、つまり黒人だから。ピコーラが、彼女が愛したシャーリー・テンプルのような愛らしい白人の女の子だったら、ここまでの不幸はなかっただろうと、ソープヘッドも理解して納得する。だから、ピコーラの願いを叶えてやったわけです。
「この食べ物を持っていって、ポーチで寝ている犬にやりなさい」
「もしあの動物がふしぎな振る舞い方をしたら、お前の願いは次の日にかなえられるはずじゃ」
ソープヘッドはこの犬が嫌いで、毒を混ぜた食い物で始末する機会を狙っていたのは確かなんですが、この時は単にピコーラを利用しただけではなく、彼女の願いを叶えてやる唯一の方法だと彼が考えていたのも確かなんでしょう。実際、犬は死んで、それを見たピコーラは自分の願いが神様に聞きとげられて叶ったのだと信じます。
そしてピコーラはついに、自分にしか見えない青い眼と、「アンタの目は誰よりも青い」と囁き続けてくれる、自分だけの友達を手に入れました。
誰も糾弾されない
とまあこんなわけで、誰か親切な人が可哀想なピコーラを救ってくれるわけでもなく、彼女の家族が絆を取り戻すこともなく、少女も家族も壊れるだけ壊れて、ピコーラの子供のためにクローディアとフリーダが植えたマリーゴールドの種は芽吹くこともない。差別を撤廃するために誰か雄々しく立ち上がるわけでもないし、シャーリーや可愛い白人の女の子の人形を拒否したクローディアが、その誇りを胸に黒人社会に変化をもたらすなんてこともない。彼女たちを取り巻く現実は現実のままで、相変わらずそこにある。
ぐ、と腹を押されるような重苦しい話ではあるんですが、それでいてただの暗い話にならずに済んでいるのは、たぶん、登場人物の全てが「自分の置かれた現実を生きている人たち」であって、この物語が彼らの誰も糾弾しようとはしていないからなのだろうと思います。
ピコーラの父も母もけっして良い親ではないわけですが、「悪い親のせいで不幸になった女の子の話」ではない。チョリーもポーリーンも「そういう現実」の中に生まれて、そのまま生きてきただけ。狂気に向けてピコーラの背を突き飛ばしたソープヘッドにせよ、そうする理由はあった。全ての原因が一つ一つ丁寧に積み重なって、自分にしか聞こえない声で話す友達に「私の目が本当に青いか」と確認し続けるピコーラに辿り着く。
クローディアやフリーダと同じ学校に通うモーリーンは、他の黒人たちより裕福で、他の黒人よりも肌の色が薄い。だから彼女は特別扱いされているし、いじめられない。 チョリーは生まれてすぐに母親に捨てられ、実父にも受け入れられることはなく、まともな親がどう振る舞うものなのか知らない。だから自分の娘にだってどう接してやるのが親として正しいのか分かっていない。
ピコーラの「青い眼が欲しい」という願いは叶うはずがない滅茶苦茶なものだけど、実際、彼女が幸せになる方法としては正しい。
そういう現実の中で、「だからこうなりました」という話であって、誰かに罪を持たせて糾弾するための話ではない。なので読み終わると「そういうことなんだな」と妙に納得するし、悲惨な現実を描いた話なのに奇妙に優しさがあったりもします。
ピコーラの母親のポーリーンは常に家族、特に夫に対して攻撃的で狷介な女性という印象で描かれていますが、彼女の視点から語られる章では、おっかなびっくり幸せなろうとしていた女の子だったポーリーンがいて、そして彼女なりの人生の形を見出して生きている様子が語られています。常に夫と争い、ある意味そうなるように仕向けているポーリーンですが、家事の腕はよく働き者で、その為に勤め先の白人の一家からはとても信頼されて愛されている。綺麗な家、綺麗な日用品、優しくて温かな雰囲気、そうしたものが全て揃った勤め先の白人一家の家はポーリーンにとって完璧な理想の家で、彼女はこの上なくその一家を愛して誠実に務めている。生来足が悪く、他の黒人からは軽んじられてきたポーリーンを、一番認めて一番大切にしてくれているのは、たぶんその白人の一家です。
登場人物の誰かを糾弾しないように、「私たち黒人がこんな悲惨な思いをしているのは、白人の差別のせい」と糾弾しているわけでもない。
この物語の中で、ピコーラを醜い黒人として苛めているのは、同じ黒人の子供。一方で「肌の色が薄い」モーリーンは他の黒人から一目置かれて特別に扱われていて、黒人社会の中でさえ、「肌が白いのは良いこと」という価値観が根付いている。登場人物たちが白人が作り上げた価値観の中にはめ込まれて生きているからこそ、「青い眼が欲しい」というピコーラの願いがあまりにも正しくて切実で、奇妙なほど納得させられるのです。
登場人物に対する筆者の視点の為に、ピコーラの悲惨な生い立ちを語りながらも読後感が優しい、というような書評もありますし実際にそうだなあとも思うんですが、率直に言って、やはり私にとっては重い物語でした。重い。なんかお腹痛い。何より、この奇妙な納得が奇妙に後ろめたい。ピコーラの「青い眼が欲しい」という願いの正しさを理解した瞬間は、正直、気持ち悪いようなゾッとするような、何とも言えない感覚に陥りました。最初に読んだ時は「しばらく読み直したくない」と感じましたが、「しばらく」読み直したくないのであって、いずれ読み直すだろうとは思っていました。もちろん書かれている内容の深さや重要さというのはありますが、それより単純に、物語として優れているし面白いからです。
結局、今も何度となく読み直す本になっています。これからも、何度も読むことになると思います。

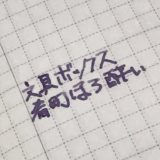

コメントを残す